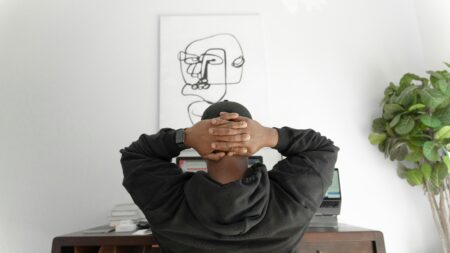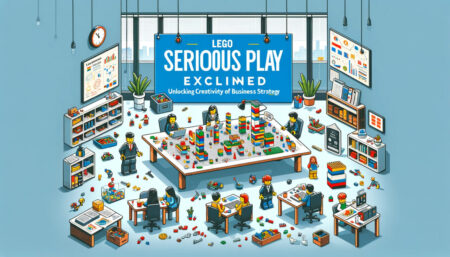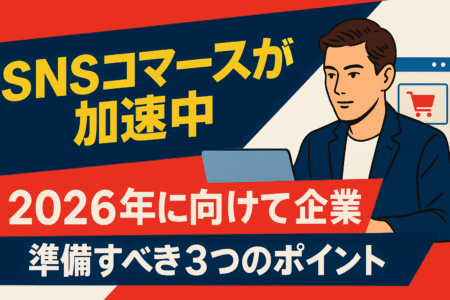モーション周期表ってなに?

Contents
1.モーション周期表って知ってる?
モーショングラフィックスをつくっている人なら、「あの動き、なんて言うんだっけ?」と思う瞬間があると思います。
そんなとき役立つのが「モーション周期表」。
化学の「元素周期表」になぞらえて、動きの基本要素を整理した一覧表のようなものです。
2.そもそも「モーション周期表」とは?
たとえば「スケール」「フェード」「バウンス」「ワイプ」など、映像の中でよく使われる動きを体系的に整理したもの。
After Effectsなどでアニメーションを作る際に、
・どんな動きが使えるか
・どう組み合わせると印象が変わるか
を可視化してくれるツールです。
もともとはデザイナー Motions Designers Collective や Motionographer が公開していた海外の「Motion Periodic Table」から広まり、
日本でも参考にして自作する人が増えています。
3.動きにも“属性”がある
周期表風に整理すると、動きにも「属性」が見えてきます。
-
E(Ease系):ゆっくり始まり、ゆっくり終わる。自然で心地いい動き。
-
B(Bounce系):弾むような動きでポップさや楽しさを演出。
-
R(Rotate系):回転を使って印象を強調。
-
O(Opacity系):フェードイン・アウトで空気感を調整。
このように分類することで、「どの動きを組み合わせると効果的か」が一目でわかります。
4.組み合わせると“デザイン”になる
単体の動きも面白いですが、複数の動きを掛け合わせると一気に映像の印象が変わります。
たとえば:
-
スケール × バウンス → 元気で弾むロゴ登場
-
フェード × ローテート → 優雅で落ち着いた印象
-
スライド × イーズアウト → 情報が自然に流れ込むUI演出
まるで化学反応のように、新しい表現が生まれるわけです。
5.周期表のように“眺める”効果
実際に周期表を壁に貼っておくと、「今日はこの動き試してみよう」とアイデアの引き出しが増えます。
デザインの参考資料としてだけでなく、
新人クリエイターの教育ツールとしても非常に優れています。
まとめ
モーション周期表は、感覚的にやっていたアニメーションを“科学的に”整理する試み。
一見感性の世界のようでいて、動きには法則や構造がある。
それを理解することで、より意図的に・効果的に魅せる動きを作ることができます。